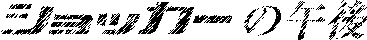
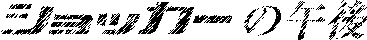
マリバロン。
数あるショッカーの女性取締役の中でも、最も美しく、そして最も冷酷残忍と噂されています。彼女の任務は訴訟対策と、社内粛正でしたので、後ろめたい覚えのある社員は、彼女と廊下ですれちがうだけでも、ドキドキしたそうです。
端正な整った顔立ちで、見事な肉体を挑発的な制服で包み、あくまでクールに話す彼女に、思いを寄せる社員も多かったのですが、浮いた噂ひとつもないのが、不思議といえば不思議なほどでした。
「ゾル大佐、ちょっといいかしら。」
ゾル大佐はちょっぴりぎくりとしました。ドアを開けておいたとはいえ、気配もなく、急に声をかけられたので。
「部屋に入るときは、ノックくらいしてほしいものだな、マリバロン。」
「あまり集中していらっしゃったので、声をかけたものかどうか、迷ったものですから。」
そう言いながら、彼女は部屋の中にすべりこむように入り、デスクの前で立ち止まりました。ゾル大佐はどちらかといえば男色の傾向がありましたので、女性にはほとんど興味を示しませんでしたが、それでも、見上げたマリバロンの美しさには、圧倒されてしまいました。
「な、何か用か。」
心中をさとられまいとしたので語気が強くなってしまい、ゾル大佐はちょっと恥ずかしくなりました。マリバロンはそんなゾル大佐の動揺を見透かしてか、首を軽くかしげ、口元に笑みを微かに浮かべました。
「ゾル大佐、よくない噂があります。」
そこでひと呼吸おいて、マリバロンはつづけました。
「大佐の狼営業部への訴訟の件で、どうもあなたはなにか画策してるという情報があるのです。私は信じたくはありませんが、もしそれが事実ならば、会社を窮地に追い込むことにもなりかねません。私は…。」
淡々と話す彼女をさえぎって、ゾル大佐は声を荒げました。
「ばかな、この私がなにを画策するというのだ。よしんば事実だとしても、貴様の関知するところではないっ。」
けれども彼女は少々もたじろがず、ゾル大佐の耳元へ唇をよせ
「ばかな真似はつつしむことよ。」
そう言い残すと微かな香水の香りを残し、入ってきたときと同じように、音もなく部屋を出ていきました。
ふん、あんな女に何がわかるというのだ。今度の一件で、相手方の弁護士は核心に迫りつつある。ずるずる訴訟を続けていれば、正体が暴露されるのも時間の問題だ。だが、あの女が気づいたとなると、早めに手を打たなければ…。
ゾル大佐はデスクの電話をとると、慌てて部下を招集しました。
+++++
世間では、ちょっとショッカーが変な会社だなと、気づきはじめていました。それでも、まだ公にはならず、警察も本気で捜査に乗り出してはいませんでしたし、マスコミでも一風変わった会社として取り上げられるだけで、ゲストとして首領が呼ばれたりする程度のことだったのです。首領はマスコミ対策として、マリバロンを使い、その美しさゆえテレビ出演も多くなったので、彼女はゾル大佐のことをしばらく忘れてしまっていました。
彼女の携帯電話に連絡が入ったのは、そういう取材を何本かこなしているときでした。伝えてきたのは、このころマリバロンの部下として働いていた地獄大使です。
「マリバロン様、大佐が動きましたっ。」
迂闊だったわ。大佐が動けないように、スネーク部隊を貼付けておくべきだったわ。マリバロンは唇を噛みしめました。
「地獄大使、スネーク部隊を出動させて。わたしも、現場へ向かいます。」
+++++
田園調布の閑静な住宅街、その暗がりで怪しげな一団があたりをうかがいながら、そろりそろりと安普請のマンションへ消えてゆきます。狼の紋章をつけた男たちが、とある玄関の前で足を止めました。呼び鈴を押し、扉が開くと、男たちは一気になだれ込みます。それっ。部屋の中には、中年の夫婦が驚いた表情でぼう然と立ち尽くしています。
「連れていけっ。」
リーダー格の男が命令すると、あっというまに夫婦を縛り上げ、信玄袋に詰めると肩に担ぎ上げました。
「大佐、奥に子供がいますっ。」
「なにっ?かまわん、連れていくまでだっ。」
まだ小さい子供を小わきにかかえ、男たちはマンションの階段を駆け降りました。通りに飛びだし、しばらく走ったところで、先頭の男が倒れました。
「どうしたっ?」
立ち止まる男たち。通りの先の暗がりから声がしました。
「ゾル大佐、あなたを逮捕します。」
若い女の声です。
「ふ、スネーク部隊か、お前らごときにこの俺が捕まると思っているのかあっ。」
言うが早いか、ゾル大佐は、異形の姿をさらけ出しながら、暗がりに向かって走り出しました。うお〜ん、うお〜ん、狼の恐ろしい声が住宅街にコダマしました。
+++++
マリバロンが現場に駆けつけたとき、大きな狼はその牙をむき、血のしたたる首をくわえ、彼女の部下を両足の強烈な爪で切り裂いているところでした。
「なんてことをしてくれたのっ。」
怒りがマリバロンの肉体を異形の戦士へと変化させていきます。大きく肩や胸の筋肉が盛り上がり、両腕両脚は短距離走の選手のように膨れ上がり、全身を青緑色に鈍く輝く鱗が覆い、赤い眼は狼をじっと見据えました。燃える炎のような赤い舌がちろちろと見え隠れします。
「正体を現わしたな、ヘビ女め。」
狼は、くわえていた首を捨てると脱兎の如く、マリバロンに襲いかかりました。マリバロンはすべるように最初の一撃をかわすと、体勢をくずした狼の背中へ毒液をかけました。
「うおっ。」
狼は背中から煙を上げながらも、体勢を立て直し、ふたたびマリバロンに鋭い牙を向けます。狼とマリバロンは、がっぷり組み合いました。マリバロンは渾身の力を込め、狼を羽交い締めにしました。骨がきしむような音をあげはじめ、何本かの骨は実際に砕けはじめたようでした。狼は苦しげなうめき声とも雄叫びともつかない声を発しましたが、マリバロンは力を緩めようとはしません。
「おのれえ。」
そのときです。不意にマリバロンの締めつける力が弱りました。マリバロンの背中から乳白色に光る巨大な牙が突き出ています。マリバロンはどうとくずれおちました。赤い血がみるみるうちに彼女のまわりに溢れていきます。
狼は赤い舌をだらんとたらしながら、立ち上がりました。狼の下腹部には、巨大な牙が赤い血をしたたらせそびえ立っています。
「手こづらせやがって。」
狼は仲間を集めると、暗やみへ走り去っていきました。
冷たいアスファルトに赤い血の海が広がります。マリバロンの意識は、微かな光をたぐりよせるように、明滅を繰り返しているようでした。次第に明滅の間隔が伸びていき、とうとうマリバロンの意識は暗やみに吸い込まれていったのです。
いつのまにか静かに雨が降りだし、マリバロンの白い裸身は、アスファルトの漆黒に鋭いコントラストを描き、さながら一枚の絵のようでした。