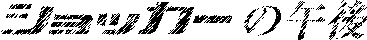
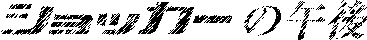
いかな大病院とはいえ、夜勤の医師は、そう多くはいません。今夜も夜勤で詰めているのは、医師一人だけでした。それでもこの病院が良心的なのは、救急医が当直を勤めている点です。救急医ならば、大概の障害に対応できるからです。病院によっては、脳外科医が当直で、外傷患者お断りなんて夜間診療指定病院もあったりするご時世ですから。
息が止まったり、鼻血が出たり何度も呼び出されて当直医辰五八六はぐったりしていました。当直室は集中治療室の階下にあって、呼び出しの度に階段を上がるので、もうかんべんしてほしいものだとお茶を飲んでいました。が、なにやら廊下が騒がしいので、おいおいまたかと、辰五八六は当直室の扉を開け廊下を覗き込みましたが、彼は自分が見たものが信じられず、呆然としました。廊下には何百という猫がうごめいていたのです。そして、猫たちの眼がいっせいに彼の方を向いたかと思うと、雪崩をうって飛び掛かってきました。彼は抵抗する間もなく、猫に埋もれていきました。
+++++
「ぱんっ。」
+++++
銃声が聞こえて、星野スミレは慌てて、病室を出ました。集中治療室は3階の奥で、病室を出ると廊下になります。左手にナースセンターがありますが、そこには誰もいません。廊下の突き当たりは非常階段、しっかり鍵がかかっています。ということは、反対側の3階ロビーのようです。星野スミレは腰の22口径を抜くと、右手に持ち、ロビーと廊下を隔てる分厚い扉の前に立ちました。
「ぱんっ。」「ぱんっ。」
また銃声です。彼女は思い切って扉を開けました。
「にゃあ、にゃあ、にゃあ、にゃあ。」
ロビーは猫の鳴き声が渦巻いてました。警官たちが何人か、階段に向かって発砲しています。階段では、白い服を着た男を警官が庇いながら、こちらへ進んできます。
「なにごとっ?」
星野スミレの問いかけに、近くにいた警官が答えました。
「猫です。猫の大群ですよっ。」
眼をこらすと、階段の踊り場あたりに、黒いもやもやがあります。それは、重なり、ひしめき合い、今や巨大なアメーバのように進んでくる猫の集団でした。彼女は銃を構え、階段へ走っていきます。
「その人はっ?」
「お医者さんです。この下で倒れていたので連れてきましたっ。」
警官に手を貸しながら、星野スミレは猫に発砲します。しかし、あまりに数が多すぎて、なんの効果もありません。ようやく階段を登り切り、一気にロビーを突っ切ります。集中治療室の扉の前で振り向いた時には、猫の巨大な塊は、ロビーを怒涛のごとく進んでくるところでした。
「中に入って。」
扉を開け、警官たちと医師を廊下に引きずり込みます。急いで扉を閉めましたが、猫が扉に押し当たる音が聞こえます。念のためにと内側の防火扉も閉めて、やっと猫の音が聞こえなくなりました。
「大丈夫?」
警官たちと医師は軽い引っ掻き傷だけのようです。
「状況を説明して。」
「何がなんだかわかりません。1階の方が騒がしいので、様子を見に行ったところ、猫の大群が押し寄せていたんです。階段のところに彼が倒れていたので、なんとか担いできたところでありました。」
医師を連れてきた警官が答えました。
「他のものは?」
「全員応答がありません、我々だけです。」
無線機で仲間を呼び出していた警官が答えます。
「…冗談じゃないわ。猫が襲ってきて、警官17名も殺られるなんて…。」
彼女はナースセンターへ行き、電話の受話器を取りました。しかし、発信音すらしません。電話線を切断されたようです。携帯を取り出し、電源を入れてみましたが、まったく不通です。どうやら電波障害も起こしているようです。彼女は薬品棚から消毒液と包帯を取ると、廊下で座り込んでいる警官たちのところへ戻ってきました。医師は、意識を回復したらしく立ち上がってしきりに頭を振っていましたが、彼女を見ると、私がやりましょうと消毒液と包帯を受け取りました。
「完全に孤立したようです。とりあえず巡査長と巡査は、治療が終わったら、防火扉と非常階段のところで見張りについてください。私は参考人の警護につきます。」
病室の中はロビーでの騒ぎが嘘のように静かなものでした。MBXは鎮静剤を打たれ、すやすやと眠っています。イオットは後ろ手に手錠をかけられたまま、ベッドの端に腰を降ろしていました。
「何かいいたそうですね。」
星野スミレが言います。けれども、イオットは無言のままです。
「まったく、猫が襲ってくるなんて…。電話線も切られて、連絡もつけられない…。用意周到ね、あなた。」
「まだ、あたしがやったと思っているの?」
イオットが口を開きました。
「おおかた、強力なマタタビかなんか使ってるんでしょう。でも、あと2時間で応援が来る。それまで、彼を守り切れる自信はあるわ。残念ね、有賀さん。」
「長い夜にならなきゃいいけど、星野刑事。」
二人はお互いの顔を見つめ、相手の真意を計ろうとしました。そのとき、ドアをノックして医師が入ってきました。
「入ってもいいかな、患者の容態を診たいんだけど。」
星野スミレが首を振って中に招きいれました。医師は、手錠をかけられたイオットにぎょっとしたようですが、部屋の奥の装置をモニターし始めました。星野スミレは、病室の入口で腕組みをしてドアによりかかって下を向いています。医師は装置のモニターを終えると、イオットの隣に立ち、患者を診察しはじめました。医師の胸のネームプレートには辰五八六と書いてあります。イオットはしばらく黙って眺めていましたが、なにげなく患者の様子を見ている医師に、突然話しかけました。
「よく、ここまで来られたわね、おとなりさん。」
医師はぴくりと肩を動かしましたが、平静を装って小声で言いました。
「やはり、ばれましたか。変装はどうも苦手でして…。」
イオットが、ふふと笑いかえすと、医師に化けた根津藤衛が続けて言いました。
「だいたい、あなたこそ、関係がないといいながら、なぜ、ここにいるんです?」
「おとなりさんが、どういうつもりなのか、何かとおせっかいなのよ。」
根津藤衛は聴診器を首にかけると、イオットの方へ体を向けました。
「おせっかいね。たしかに、そうだな。なぜ、あなたにあんな話しをしたのか、実は僕にもわかりません。でも、あなたは僕を止められませんよ、絶対にね。」
そう言いながら、扉のところで廊下の方を向いて何か指示している星野スミレの背後に忍び寄ります。根津藤衛の手が、凶暴な爪が伸びたネコ科の前足へと変化しはじめました。その手を大きく振り上げ、星野スミレを引き裂こうとした瞬間、イオットが叫びました。
「星野刑事っ、そいつはニセ医者よっ。」
星野スミレの動きは鍛え抜かれたものだけが見せる素晴らしいものでした。振り降ろされる腕をかわし、廊下へ飛びだしながら、体をひねり、45口径を構えます。
「ぐるるるる…。」
銃口が向けられた場所には、医者の白衣を着た大きな黒豹が唸っていました。
「…あ、あなた、何者?」
星野スミレは目の前にいる、化け物が信じられず撃つのをためらいました。黒豹は、がうと唸ると大きな口を開けて、星野スミレに飛びかかります。彼女が45口径の引き金を引くのと同時に、彼女の肩に痛みが走りました。
「ばぁんっ。」「がううう。」
黒豹は廊下の壁で反転すると、跳躍し病室のベッドを一気に飛び越え、窓ガラスを割り、表へ飛び出していきました。星野スミレは、病室の窓から表を見ましたが、暗闇に紛れ込んでしまったようで、黒豹を見つけることはできませんでした。
「星野刑事の弾、当たったみたいよ。」
左肩を押さえながら、星野スミレは振り向き、イオットの方を向きました。イオットが顎で指し示した床からベッドには、血痕が点々とついていました。
「なんなの、今のは?」
イオットは、肩をすくめたまま何も語りません。憮然とした表情で星野スミレが立ち尽くしていると、警官たちが押っ取り刀で病室に入ってきました。
「な、なんですか、今のは。でっかい猫みたいな…。」
「なんだかわかりませんが、とりあえず、逃亡したようです。あなた達は持ち場に戻ってください。また来るかもしれないから。」
警官達は、猫の親玉だとか、ライオンだとか言いながら、廊下に戻っていきました。
「治療してあげるから、手錠を外して。」
イオットが言いました。星野スミレの左肩は出血してブラウスが真っ赤になっていました。星野スミレが躊躇した様子を見せていると、
「じゃあ、片手でもいいから、外して。ひとりじゃ、できないでしょう?」
とイオットが言いました。たしかに、左肩では1人では包帯を止めることすらできません。しかたなく右手の手錠を外し、あらためて片方をベッドに繋ぎます。イオットは自由になった右手を2、3度振りました。星野スミレは、ホルスターを外すと、血に染まったブラウスを脱ぎ、椅子に腰かけました。傷はそう深くはありませんでしたが、背中から肩口にかけて、爪の跡が4本長く筋を引いていました。イオットは傷口を消毒しながら、彼女にブラも外すように言いました。星野スミレの形の良い乳房がこぼれます。ひゅうとイオットは口笛をふきましたが、星野スミレに睨まれたので、黙って包帯を巻きました。片手で手慣れた様子でイオットが包帯を巻いてしまうと、星野スミレはフロントホックのブラを付け直し、ボロボロになったブラウスはあきらめて、直にホルスターを肩から下げました。ホルスターに45口径を収め、左肩を2、3度ぐるぐる回すとイオットに向き直りました。
「…ありがとう、一応礼を言います。」
「どう、いたしまして。」
「…さっきの、また来るのかしら?」
「そうね、坊やを殺すまでは、何度でも来るわ、きっと。」
二人は、ベッドのMBXを見ました。MBXはすやすやと寝ているようでしたが、突然鼻から血がつうと流れ出ました。二人はびっくりして、彼を見つめましたが、星野スミレが声を上げました。
「ああっ、あなた、見てたのねっ。」
MBXはさっきの騒ぎで目が覚めたのですが、恐かったので寝たふりしてたようです。
「あ、い、いいえ、オッパイなんか見てませんっ。」
あわててMBXは否定しましたが、流れ出てくる鼻血が全てを物語っていました。星野スミレは、MBXの鼻にティッシュを無理やりつっこむと、ぷいと病室を出ていってしまい、イオットはくすくすと笑いました。
+++++
病室から飛び降りた、根津藤衛は裏庭の木の根元まで戻ってきていました。左足に当たっていた銃弾を爪で取りだすと、ヒトの姿に戻り、置いてあったデイパックから、煙草を1本取りだし、火をつけます。にゃあ、にゃあと遠くから猫の声がしていました。何かを考え込むように、座り込んでいましたが、そのとき携帯が鳴りました。
「ネットヘッズです。」
電話は上司のドッグファザーからでした。
「お見舞いは終わったのか?」
「…まだです。意外に手ごわくて。」
「さっさとおしまいにしろ。地獄大使から催促がきている。」
「…。」
「失敗するようなら、貴様の処遇は考えさせてもらうからな。」
それだけ言うと、電話は切れました。くそ、いい気なもんだぜ。現場がどれくらい苦労してるか、ちっとも分かろうとしやしない。根津藤衛は煙草を投げ捨てると、病院の電気がついている部屋を見上げました。…有賀イオット、あの女、どう動くつもりなのか…。闇の中で投げ捨てた煙草の赤い火が、かすかに揺らいだような気がしました。
+++++
煙草の赤い火はきれいな放物線を描き、道路の反対側へ飛んでいきました。夜明けには、まだまだ早い横浜の街は、人気もなくしんと静まり返っています。
「坂さん、だから、飛ばしすぎっていったでしょう。」
リヤシートからマロが話しかけました。坂は、手にしていた赤い紙を丁寧に折りたたみ、財布にしまうと、
「ふん。スポーツカーとスピード違反は切っても切れない仲なんだよ。」
そう言い捨てると、ランチャのエンジンに火を入れました。目的地までは、もう十数分のところです。ローレックスの腕時計で時間を確認し、約束の時間にはまだ間があるなと思った坂は、たしかに飛ばしすぎたかもしれんと独り言を言いながら、ランチャを手近なファミレスの駐車場に入れました。
「とりあえず、時間をつぶすか。」
坂がそう言うと、一眠りして腹が減っていたのか、マロは少し嬉しそうな顔をしました。
+++++
壊れたパワーブックの液晶がかすに明滅しています。映し出された画像を、イオットは黙って見ていましたが、やがてくすりと笑うと独り言のように言いました。
「たしかに、これじゃそっくりよね。」
液晶画面の中の女性は、青い眼をして、短い金髪に薄いピンク色のナースキャップ、少し焼けた肌が覗く白衣をつけ、大きな翼で宙に浮いています。今のイオットと違うところは、その翼がないことと、絵の方のスカートが少し短いことくらいでした。
「すいません。」
「坊やがあやまることはないのよ。」
「でも、僕がこんなもの描かなければ…。」
「いいの、綺麗に描いてもらえて光栄だわ。」
イオットは自由な方の手を伸ばし、MBXの体に触れました。
「イオットさん、何があったんですか…。」
「坊やは、何か見たの?」
「…銃声がして、イオットさんが裸で自転車乗ってて、それで、後ろから撃たれて…。」
「じゃ、それだけよ。」
「でも、刑事さんから聞きました。殺人事件だって、…イオットさんがやったんですか?」
イオットが何か言おうとした時、天井の照明が消え、一瞬真っ暗闇になりました。すぐに、どこか遠くでエンジンの始動音がして、非常用照明に切り替わりました。
「なに、今のは?」
慌てて星野スミレが病室に入ってきます。
「誰かが電源を落としたようね。」
非常用発電機が動いていましたが、電力をセーブするため、照明はぼんやりとした明るさにしかなりません。
「星野刑事、危険だわ。手錠を外してもらえない?」
「それは、できません。」
イオットは星野スミレを睨みつけましたが、彼女はそれを無視すると、廊下に向かって、来るわよと大声で怒鳴りました。ほどなく、防火扉に体当たりする音が聞こえ始め、星野スミレは両手に銃を構え病室の前に立ちました。防火扉は、しばらく持ちこたえていましたが、やがて、めりめりめりっと破れ、猫がなだれ込んできます。前方にいた警官3人は、たちどころに猫の波に飲み込まれ見えなくなってしまいました。
「ぱん。」「ぱん。」
飛び込んでくる猫を片っ端から銃で撃ちましたが、いかんせん数が多すぎます。猫の波はあっという間に廊下を埋め尽くし、星野スミレは退却を余儀なくされました。病室の扉をなんとか閉めて、紛れ込んだ猫を撃ち殺すと、星野スミレはスカートの中の銃をイオットに渡しました。イオットが怪訝そうな顔をすると
「信用したわけじゃありませんけど…。」
と、星野スミレが言いました。廊下側の窓ガラスにひびが入り、きしみはじめました。二人が銃をかまえた、その時。
「にゃあ、にゃあ、にゃあ、にゃあ。」
とつぜん、天井から猫がふってきました。ガラリの外れた換気口から、数百の猫が入ってきたのです。こうなると、もう銃は撃てません。MBXを覆い尽くそうとする猫を、殴りつけ、つかんでは投げ、壁にたたきつけるの繰り返しです。さいわい、猫らしくない凶悪な爪と牙を持つとはいえ、しょせん体の小さい猫です、投げ飛ばされ壁に体を打ちつけられると、ほとんどはそのままのびてしまいました。とはいえ、数百匹からの猫です。イオットの白衣は破れ、体中引っ掻き傷だらけ、あたりは血の海です。ようやく、動いている猫より動かなくなった猫の方が多くなったころ、ついに廊下側の窓が割れ、第2陣が飛び込んできました。
「にゃあ、にゃあ、にゃあ、にゃあ。」
今度は猫たちの中にひときわ大きい黒い影がまじっています。
「がうううぅぅ。」
大きな黒い影は真っ直ぐMBXに飛びかかります。イオットはMBXの前に立ち塞がり黒い影を真正面から受け止めました。黒い影と見えたものは、根津藤衛が変化した黒豹でした。
「なぜ、邪魔をする。がうう。」
黒豹はイオットの右腕に噛みつこうとしましたが、イオットは逆に片腕で黒豹の首を絞めつけます。見かけによらず、イオットの腕の力は強く、黒豹は振りほどこうともがきしたが、その前足がイオットの白衣をむなしく引き裂くばかりでした。
「星野刑事、こいつが親玉よっ。撃って。」
星野スミレは後から後から湧いてくる猫達を、パワーブックをバット代わりに殴りつけていましたが、イオットの声に気がつくと、45口径を黒豹めがけて連射しました。
+++++
「ずだんっ、ずだんっ、ずだんっ。」
+++++
イオットが黒豹を締めつけている右腕の力を弱めると、黒豹はイオットの体を離れ、床にどうと倒れました。
「ぐるるるるぅぅぅ。」
苦しそうに肩で息をしていましたが、次第にその動きも緩慢になると、全く動かなくなり、そしてまるで蒸発するようにその体が消えていきました。あれほど荒れ狂っていた猫たちも、急におとなしくなり、逃げ帰るように散っていきます。
「…これで、終わりなの?」
星野スミレの問いかけに、イオットは答えず、さっきまで黒豹が倒れていた床を見つめています。その表情に漠然とした不安感がよぎりましたが、それがなんなのかはイオットにもわかりませんでした。星野スミレは、まだ左手に握っていたパワーブックに気がつき、首を振りました。
「…これ、借り物なんだけどなあ…。」
さしものパワーブックも、バットがわりに猫をホームランされては、もはや原形をとどめていません。凶嫁舞刑事になんて説明するか考えていると、ベッドでMBXがううと唸りました。
「だいじょうぶ?」
見るとMBXは、またもや鼻血を出しています。でも、それも仕方ありません。猫との乱闘で、イオットも星野スミレも、衣服はおろか下着までなくなり、裸同然の格好で立っていたのですから。
+++++
浅草の安アパート、開いた窓にぶら下がった風鈴がちりんちりんと時々悲しい音を鳴らし、ちゃぶ台に置かれた2台のモニターは沈黙したまま、街の明かりをぼんやりと反射しています。涼しい穏やかな風がそうっと吹き込んで、また風鈴を鳴らしました。すると、それが予定されていたかのように、パソコンがじゃあんと音を立て、モニターが明るくなりました。画面中央に「?」マークが点滅していましたが、「Net heads to go」という文字が浮かび上がると、ダイアログのグラフがゆっくり伸びていき、ぱっと画面が暗転しました。再び暗くなったモニターに、何かがきらりと光りました。それは小さい2つの点で、ゆらゆらと動いたかと思うと、画面の端に消え、それきり現れることはありませんでした。ハードディスクの微かにちりちりいう音にあわせ、天井裏で物音がしたような気がしましたが、やがて明るくなる夏の夜明けに、その気配もかき消され、4畳半の部屋には夏の日差しの予告編が差し込みつつありました。