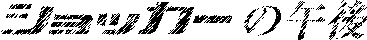
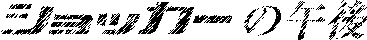
西向きの開け放たれた窓から、夏の午後の高角度の陽射しが差し込んでいました。アパートの2階の部屋。となりは幼稚園の庭なので、遮るものはなく風通しはいいのですが、ひきかえに太陽はじりじりと部屋の温度を上昇させていました。エアコンなんかはありません。小さな、ぶうんと音を立てる扇風機が、循環した熱い空気を男に吐きかけていました。男はモニターを2つ並べたコンピュータに向かい、羅列した文字を食い入るように眺めていましたが、ビールをひとくち飲むと煙草に火をつけました。ほうっと青白い煙を吐き出し、おもむろにリターンキーを押し、画面に現れた棒グラフがゆっくり進んでいくのを確認すると、ようやく画面から顔を上げ、窓のほうを向きました。外では、朝から聞こえているサイレンの音が、接続が切れかけたスピーカのように断続的に鳴り響いています。幼稚園の子供たちは早々と引き上げたらしく、いつもなら聞こえてくる子供たちの歓声が今日は一切ありません。男は短く刈り上げた頭を撫で、またビールをひとくち呷りました。
+++++
+++++
深い、深い、夢さえ見えない深い眠りの中で、イオットは自分の足にからみついてくる何かを感じました。とても懐かしく、愛情の高ぶりと強い保護の感情。ああ、あたしは疲れているのよ。彼女は寝返りをうちました。ですが、足元のそれは、ますます強く明確にからみついてきます。小さな暖かい手が彼女の足元に時々そっと触れ、首すじに回り、髪を撫で、小さなやさしい息遣いが聞こえます。おねいちゃん…。彼女の心は強く揺り動かされました。記憶の糸車は歯止めを失い、大きくかたんかたんと回り始めたようでした。
+++++
おねいちゃん、おねいちゃん。疲れて横たわっていると、妹が遊んでほしくて、まとわりついてきました。
「あたしは、疲れてるの。あんたとなんか遊ばないの。」
つっけんどんに言い放ったのは、有賀イオット、この春中学を卒業し、となり町の印刷工場で働いている16歳になったばかりの少女です。姉に邪険にされ、部屋のすみで小さくなったのが、彼女の妹アンジェラです。アンジェラは今年6つになるのですが、発育が悪く病弱で、平均的な6歳の女の子に比べれば身長も低く、体重は抱いてみるとぎくりとするほど軽く、そのせいか内向的な性格でした。なので近所の子供たちにはついていけず、昼間、姉が仕事に行ってしまうと、家に閉じこもり、母の内職の傍らで、ひとり遊びの毎日なのです。自然、遊び相手は姉だけになっていたのです。
イオットは体をおこすと、部屋のすみでじっとしている妹に声をかけました。
「おいで。」
イオットが両手を差し出すと、それまでふさぎこんでいたアンジェラの顔が、ぱあっと明るくなりました。イオットは妹を抱きかかえました。アンジェラは頭をイオットの肩に乗せ、小さな手を彼女の背中に回し、しっかりと抱きついています。妹の体温がイオットに伝わり、かすかな呼吸の音が聞こえました。アンジェラは、たどだとしい言葉使いで自分と人形の今日一日を話しました。それは、とりとめもない話でしたが、イオットはいちいち頷くと、やさしく髪を撫でてあげました。そのうちアンジェラは寝てしまいました。眠ってしまった妹を、イオットは布団に寝かしつけ、その寝顔をいつまでも見つめていました。
+++++
イオットの母は16のとき、集団就職で東京にやってきました。けれども、憧れの東京での楽しい日々は、ほんの一瞬でした。就職した会社が倒産し、住む場所も追われて、水商売の道へ。若いフランス人の絵描きと恋に落ち、妊娠したのがわかったのが、その年の秋でした。相手の男は幾ばくかの手切れ金を渡すと行方をくらまし、母は身重の体をかかえて、内職でなんとか食いつなぎ、イオットを出産したのでした。出産後何度かまっとうな仕事につこうとしましたが、乳飲み子を抱えた女ができる仕事は少なく、結局場末の売春宿につとめるのが関の山でした。
母の仕事にうすうす勘付いたのは、イオットが小学生になったころです。もともと学校では浮いた存在だったのですが、いじめられたとき、髪の毛の色や瞳の色以外のことで、悪口を言われたのがきっかけでした。母は家では仕事のことを一切、口にしなかったので直接たずねたりはしませんでしたが、近所のおばさんたちの会話の端々でなんとなく理解はできたのです。母は、イオットを育てるため、昼間は内職をして、夕方になると仕事にでかけ、帰るのは明け方、そういう日々の繰り返しでした。しかし母は、愚痴ひとつこぼさず、父の悪口さえ言わず、彼女を育て上げました。
小学生の高学年になったとき、イオットには突然妹ができました。それは、ある朝イオットの目が覚めると、となりに寝ていました。あなたの妹、アンジェラよ、母が言いました。母が妊娠していたわけではないのは、イオットも知っていました。たぶん、その子は母の仕事仲間の子で、以前見かけたことがあったような気がしました。実はその子の母親は、若い男と駆け落ちしてしまったので、その子は施設に入れられるところだったのです。でも、イオットの母が不憫に思い、引き取ってきたのですが、それは後で知った話です。アンジェラは愛くるしい顔をして、静かに眠っていました。
その日から、3人の生活が始まりました。昼間は母が内職をしながら、アンジェラの面倒を見ます。イオットは学校が終わると、急いでうちへ帰って、入れ替わりに母は仕事へ行き、今度はイオットが妹の子守りをすることになりました。アンジェラは2歳になるというのに、まだ足元がおぼつかず、上手く歩けないので、イオットは彼女を負ぶってはよく表を散歩に行ったものです。アンジェラは病気がちで、よく入退院を繰り返しました。その都度、高額な医療費が必要になり、蓄えも次第に少なくなり、イオットも近所のスーパーでアルバイトしたり、母の内職の手伝いをしたりするようになりました。そんな暮らしを4年間続け、イオットは中学を卒業する年になりました。高校へ行く学力は充分ありましたが、彼女の家にそんな余裕はもう残っていませんでした。それでも、イオットはわがままも言わず、当然そうするのが当たり前のように、となり町の印刷工場へ就職したのでした。就職したとはいっても、中卒の安月給です。暮らし向きは若干よくなりましたが、あいかわらず母は仕事に行かねばなりませんでした。午後3時に母が仕事に行ってしまうと、アンジェラはイオットが帰ってくる8時過ぎまで、1人で留守番です。気掛かりなのは山々なのですが、保育園に入れるお金もなく、仕方のないことでした。心配なのは、1人でいるときに病気の発作を起こしたりすることです。イオットは仕事が終わると大急ぎで帰り、無事でいる妹を見てほっとするそんな毎日でした。
アンジェラはイオットが大好きでした。必ず、今日一日の報告をして、イオットに抱かれて眠るのが日課でした。おねいちゃん、おねいちゃん。イオットが休みの日には、1日中くっついて離れません。イオットはちょっとうるさく感じるときもありましたが、できるだけアンジェラの側にいてあげるようにしていたものでした。
+++++
アンジェラの寝顔を見ているうちに、いつのまにかイオットも眠ってしまっていたようです。どかどかどかっ、という荒々しい足音に続き銃声と怒号が轟き、驚いて眼が覚めました。銃声はすぐ止みましたが、数人の武装した男たちが、母に銃をつきつけながら、部屋の中に入ってきました。
「おかあさんっ。」
状況がわからず、イオットは慌てました。
「落ち着いて、イオット。」
母は後から羽交い締めにされ、銃を顎につきつけられていましたが、優しくイオットに言いました。
男たちは、どうやら最近流行りのなんとか解放戦線のようでした。ここ2、3日ラジオで聞いたことがありました。なぜ、それがこんなところに来たのでしょう。彼らは、警察に追われ、イオットたちと同じアパートに潜伏していたようなのですが、潜伏先が発見、警察に急襲され、ちょうど帰宅したところの母を人質にとったのでした。
「人質を解放して、おとなしく出てこいっ。どうせ逃げられんぞっ。」
表から拡声器の声がします。
「うるさいっ、警官を下げろっ。さもなくば、命の保証はないぞっ。」
解放戦線の男が応じます。部屋のすみで、イオットとアンジェラと母は、3人で寄り添い抱きあいました。だいじょうぶよ、イオット、だいじょうぶよ、アンジェラ。お母さんがついてるわ。母は2人の娘に繰り返しました。警察と男たちのやりとりはしばらく続き、長期戦になるかと思われたアパートの攻防は、意外なことにあっけない終焉を迎えました。
表が静かになり、警察からは何の動きもなくなって膠着状態に入ったかに思えた瞬間、突然、部屋に催涙弾が撃ち込まれました。つづいて突撃の声が上がり、警官が発砲し始めました。もうもうたる煙と銃声と罵声の中、母は必死に娘たちを抱きしめました。だいじょうぶよ、おかあさんにつかまって。警官が階段を駆け上がってくる足音が聞こえました。だだだだだっ。解放戦線の男たちは、窓の外に向かって発砲しつづけていましたが、ひとりの男が突入してくる警官に気づき、こちらを向きました。男は自動小銃をかまえると、扉に向かって数発撃込み、まだ硝煙ののぼる銃口を母娘に向けました。
「冥土の手土産だっ。」
男が引き金に指をかけ、まさに銃弾を発射するその刹那、母が立ち上がり男に飛びかかりました。
+++++
ずががががががっっ。
+++++
甲高い自動小銃の銃声が鳴り響きます。母の背中から何発も高速の銃弾が飛びだし、弾丸の後を追うように、血液が噴きだしました。それでも、母は止まらずに男の喉元へ、爪を突き刺しました。彼女の爪が男の喉を突き破り、その先端が気道に達しました。男はひゅぅと小さく息をもらし、母もろとも床に倒れ込みました。
「…おかあさんっ。」
イオットはようやく声を出し、母を呼びましたが、すでにぴくりともしませんでした。声に気づいて、別の男がイオットの方を向きました。
「あっ、このアマっ。」
男は倒れている仲間に駆け寄りましたが、すでに絶命していました。男は絶叫しながら、すでに動かなくなっている母に拳銃を2発発射し、妹を抱きしめているイオットに近づいてきます。男の眼は尋常ではありませんでした。イオットは恐怖で身動きすらできません。男は妹の背中に銃口をつきつけると、引き金を引きました。
+++++
がんっ。
+++++
鈍い音がして、イオットは腹部に鈍痛を感じました。彼女を握りしめる妹の手の力が一瞬痛いほど強くなって、次の瞬間その手はだらりとたれ下がりました。
+++++
「突入っ。」
大声で号令がかかり、扉をけやぶって警官が乱入してきます。妹を撃った男は、ゆっくり呆けたように、扉の方へ顔をむけましたが、その目が何かをとらえる前に、男の頭は水平射撃された催涙弾で、窓の方へ吹っ飛んで行きました。
「大丈夫かっ。」
「少女を保護しましたっ。」
そんな声が聞こえた気がしましたが、イオットの視界はすうっとカーテンがおりるように、真っ白になっていきました。
+++++
+++++
アンジェラ…。
自分の声に、イオットは眼を覚ましました。さっきから足元を動いていたのは、どこから来たのか、1匹の小さな猫でした。
「おいで。」
イオットが手を差し伸べると、猫は寄ってきて彼女の腕の中におさまりました。ここは、浅草の安アパート。大きく開いた西向きの窓からは、夕暮れとなったのか、オレンジ色の光が差し込んでいます。イオットは猫を抱いたまま、窓際に立ち、表を見やりました。猫の足が下着姿の彼女の敏感な部分を刺激しました。彼女は右手の中指で、腹部の傷跡にそっと触れました。
アンジェラ…。
+++++
猫がイオットの腕をすりぬけ、せまい4畳半の部屋を横切り、玄関へ走っていきました。
「あ、待って。」
イオットが、後を追って玄関へ行くと、ノックの音がします。こんこん。扉を開けると、短く刈った髪をジェルで立たせた、痩せぎすの男が立っていました。男は、顔を出したのが金髪碧眼の下着姿の女性だったので、一瞬ひるんだ様子を見せましたが、白い歯を見せて無理に微笑むと彼女に言いました。
「あ、その猫、僕のなんだ。邪魔しちゃったようだね。」
イオットは何も答えず、男を睨み返します。
「…ぼ、僕は、となりの部屋に住んでいる根津藤衛。皆はネットヘッズって呼んでる。」
男は頼みもしないのに自己紹介をしました。
「そう、用はそれだけ?」
イオットは扉を閉めようとしました。男はあわてて、つづけました。
「あ、いやいや、あのう、君、今朝引っ越してきたばかりだろ。ほら、荷物の整理とかで大変だろうと思ってさ…。」
そして首を伸ばして室内を覗き込もうとしましたが、イオットが体を動かして視線を遮りました。
「…い、いや、それにさ、なんか今日は近所の店、全部閉まっちゃっててさ、買い物にも行けないから、これ、よかったらどうかなと思って…。」
男はそう言いながら、菓子パンを差し出します。
「ありがとう。でも、結構よ。用がそれだけなら、閉めるわよ。」
扉のノブに手をかけようとしましたが、男はまだ何か言いたそうです。イオットは首を小さく振り、男に言いました。
「ああ、あたしは、イオット。有賀イオットよ、よろしくね、おとなりさん。」
ぶっきらぼうにそう言うと、イオットはまだ呆然と立っている男の鼻先で扉を閉めました。
根津は足元で体をすり寄せている猫を抱え上げると、さっきまでのにやけた表情とは打って変わって、冷たい眼を見せました。
「アリガ、イオット、ね。うふふ。」
根津は持っていた菓子パンを握りつぶし、自分の部屋へゆっくりと引き上げて行きました。
+++++
+++++
「…彼女はなんとか助かりそうですが、妹と母親の方は駄目でした。手遅れだったんです。。」
「…そうか、あの娘になんて説明すればいいのか…。」
+++++
白い病室の壁の小さな染みを、さっきからじっと見つめていたことに、イオットは気づきました。眼をそらし、窓の方へ視線を移しましたが、気になって、また元のところへ戻しました。染みはもやもやと大きくひろがり、もはや染みではなく、1人の老人の姿に変っていました。老人は、黒いマントを羽織り、真っ白な頭髪をもじゃもじゃと生やし、骨張った顔つきで、まるで死神のようでした。
「君は知らないだろうが、私は、君の父親の古い友人だ。。」
くぐもった声で老人は語りました。
「そして、君のお母さんの友人でもある。」
お母さんという言葉を聞いて、イオットの肩がびくっと震えました。
「私といっしょに来ないかね。話あうことは多いはずだ。」
老人はマントをばっと広げると、イオットを抱きかかえ、今度は彼女をマントで覆いました。
「…さあ、私と行こう、イオット。多くの命が流れすぎた。この世界には哀しみだけしか、残されていないのかもしれないが…。」
いつのまにか、老人の腕の中で、イオットの瞳からはとめどなく涙が溢れ、いつ枯れるともしれないほどでした。